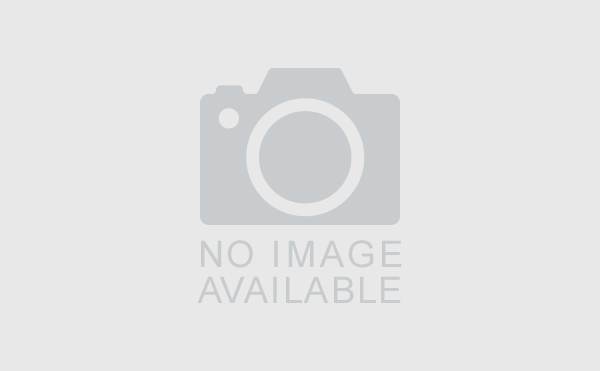実CVと媒体CV(広告管理画面・GA4)の数が違う理由
乖離が発生する要因
広告媒体ごとのデータ重複
実売数と広告管理画面上のコンバージョン数が乖離してしまう要因のひとつに、広告媒体ごとの重複計測があります。これは、多くのユーザーが複数の広告を経由してコンバージョンに至るため発生します。例えば、ユーザーが最初にGoogleの検索連動型広告をクリックし、その後Facebook広告を経由して最終的に商品を購入した場合、両方の広告媒体でそれぞれコンバージョンとしてカウントされることがあります。これにより、実際には1件の購入であるにもかかわらず、広告管理画面では2件のコンバージョンが記録されるという現象が起きます。
また、同じ広告プラットフォーム内でも重複は発生します。例えば、Google広告の場合、検索連動型広告とディスプレイ広告の両方に接触したユーザーがコンバージョンに至った際、最終クリックのアトリビューションモデルに基づき、最後にクリックされた広告にのみコンバージョンが紐づけられます。しかし、他のプラットフォームでは異なる計測基準が採用されていることもあり、結果として重複が生じやすくなります。特に、ユーザーの検討期間が長い商材やサービスでは、複数の広告に接触する機会が増えるため、この重複問題が顕著になります。このような状況を放置しておくと、広告効果を過大評価してしまい、適切な意思決定を行う妨げとなることがあります。
間接的なコンバージョンの合算
広告管理画面上のコンバージョン数が実売数を大きく上回る要因として、直接的でないコンバージョンが合算されているケースも考えられます。特に「ビュースルーコンバージョン」がその代表例です。ビュースルーコンバージョンとは、ユーザーが広告をクリックせずに表示だけを見た後、一定期間内に商品を購入した場合でもコンバージョンとしてカウントされる仕組みです。この指標は、広告の間接的な効果を測定するためには有効ですが、実売数との乖離を生む原因にもなります。
例えば、Facebook広告やTwitter広告などのプラットフォームでは、ビュースルーコンバージョンがデフォルトで計測対象に含まれていることが多いです。これにより、実際には広告をクリックしていないユーザーのコンバージョンも成果として計上されることになります。その結果、広告管理画面上の数値が実際の売上以上に膨らむことがあるのです。
また、各広告プラットフォームによってビュースルーコンバージョンの計測期間や基準が異なるため、複数の広告媒体を利用している場合は特に注意が必要です。たとえば、ある媒体では広告表示後1日以内のコンバージョンを計上するのに対し、別の媒体では7日以内と設定されていることがあります。このような違いが積み重なることで、全体のコンバージョン数が大きく増加し、実売数と乖離してしまうのです。
広告効果を正しく評価するためには、ビュースルーコンバージョンをどの程度含めるかを慎重に検討する必要があります。場合によっては、クリックスルーコンバージョンのみを重視した分析を行うことで、より実態に即した数値を把握できるでしょう。さらに、クライアントや上司への報告時には、ビュースルーコンバージョンが含まれていることを明示し、数値の解釈に対する誤解を避けることも重要です。
コンバージョンタグの正確な読み込みができていない
広告運用において、コンバージョン数と実売数の乖離が発生する大きな原因の一つが、コンバージョンタグが正しく読み込まれていないことです。コンバージョンタグは、ユーザーが広告を経由して商品を購入したり、特定のアクションを完了した際に、その成果を測定するために使用されます。しかし、このタグが正確に動作していないと、実際の成果が計測されなかったり、逆に誤ったデータが記録されたりすることがあります。コンバージョンタグの問題には、設定ミスや技術的なトラブルなど、いくつかの要因が関与している可能性があります。
CV設定、まずは正しく設定できてる?
まず確認すべきは、コンバージョンタグ自体の設定ミスです。タグをウェブサイトに設置する際、指定された場所に正確に埋め込まれていないと、正常に機能しません。例えば、コンバージョンページにタグを設置する際に、間違った位置に埋め込んでしまった場合、ユーザーがそのページに到達してもタグが読み込まれず、コンバージョンが計測されないことがあります。また、タグのコードをコピー&ペーストする際に、不要なスペースや改行が含まれてしまうと、タグが正常に作動しない原因となります。さらに、複数の広告プラットフォームを利用している場合には、それぞれの媒体が指定するタグを適切に設置しているかどうかを確認する必要があります。例えば、Google広告用のタグとFacebook広告用のタグでは設置方法やコードが異なるため、同一のタグで代用しようとすると計測エラーが発生することがあります。
また、タグマネージャーを使用している場合には、その設定ミスにも注意が必要です。例えば、Googleタグマネージャーを利用してコンバージョンタグを管理している場合、トリガーの設定が正しくないと、意図したタイミングでタグが発火しません。特定のURLパターンに基づいてタグを発火させる場合には、正規表現の記述ミスが原因でタグが発火しないこともあります。このような設定ミスは見落としがちなポイントであり、定期的な確認とテストを行うことが重要です。
何かしらの理由でタグが読み込まれてないかも
設定が正しい場合でも、技術的なトラブルによりコンバージョンタグが正常に読み込まれないことがあります。たとえば、ユーザーがコンバージョンページに到達したものの、ページの読み込みが途中で停止してしまった場合、コンバージョンタグが最後まで読み込まれずに計測が行われないことがあります。また、ユーザーのブラウザ設定や使用している拡張機能が原因で、コンバージョンタグの読み込みがブロックされてしまうこともあります。特に、広告ブロック系の拡張機能やプライバシー保護機能が強化されたブラウザでは、トラッキングタグの読み込みが妨げられるケースが増えています。
さらに、ユーザーの操作による予期せぬ挙動もコンバージョンタグの読み込みに影響を与えることがあります。例えば、ユーザーがコンバージョンページを開いた直後にブラウザの「戻る」ボタンを押したり、ページの再読み込みを行った場合、同じコンバージョンが複数回カウントされることがあります。また、コンバージョンページを開いたまま一定時間放置し、その後再度ブラウザを操作すると、再びタグが発火し、重複してカウントされることもあります。このようなトラブルを避けるためには、コンバージョンタグの設定時に「初回のみカウントする」設定を導入することで、同一セッション内での重複カウントを防ぐことができます。
また、ウェブサイトのメンテナンス作業中にも注意が必要です。例えば、サイトの管理者が広告クリック後の同じブラウザでコンバージョンページの改修作業を行った場合、意図せずにタグが読み込まれ、虚偽のコンバージョンが記録されることがあります。このような事態を避けるためには、開発環境と本番環境を分けて作業を行い、テスト用のブラウザやIPアドレスを除外する設定を施すことが有効です。
このように、コンバージョンタグがきれいに読み込まれない原因には、設定ミスから技術的なトラブルまで多岐にわたる要因があります。正確なデータを取得するためには、タグの設置や設定を慎重に行い、定期的な動作確認を欠かさず行うことが重要です。また、予期せぬトラブルを防ぐための対策も講じることで、実売数とコンバージョン数の乖離を最小限に抑えることができるでしょう。
コンバージョンのカウント方法の違い
コンバージョン数と実売数の乖離を引き起こす大きな要因の一つとして、コンバージョンのカウント方法の違いがあります。広告管理ツールには、同じユーザーが複数回コンバージョンに至った場合、そのカウント方法を設定する機能があります。代表的なカウント方法として「総コンバージョン」と「ユニークコンバージョン」の2つが存在します。総コンバージョンは、同じユーザーが同一の広告を経由して複数回コンバージョンした場合、その回数分を全てカウントする方法です。一方、ユニークコンバージョンは、同じユーザーが複数回コンバージョンを行っても1回としてカウントします。
この設定の違いは、商材やサービスの性質に応じて最適な方法を選ぶ必要があります。例えば、オンラインショップのように同一ユーザーが複数回購入することが想定される場合は、総コンバージョンで計測する方が実態に即したデータを取得できます。一方、会員登録や資料請求といった、基本的に1ユーザー1回しか行わないアクションを測定する場合は、ユニークコンバージョンで計測するのが適切です。
このカウント方法の違いを把握せずに分析を進めてしまうと、実売数と大きな乖離が生じることがあります。たとえば、実売数はユニークな購入件数で集計しているのに対し、広告管理画面では総コンバージョンで集計している場合、広告効果が実態以上に良好に見えることがあります。こうした誤解を避けるためには、各媒体の計測設定を正確に理解し、実売数との整合性を取ることが重要です。また、クライアントや上司への報告の際には、どのカウント方法で数値を算出しているのかを明確に伝えることで、誤解を防ぐことができます。
広告管理画面のコンバージョン日と実際の売上日がズレる
コンバージョン数と実売数の乖離が生じるもう一つの要因は、広告管理画面上のコンバージョン日と実売日がズレていることです。多くの広告管理ツールでは、コンバージョンが発生した日ではなく、広告がクリックされた日にコンバージョンを計上する仕組みを採用しています。これは、アトリビューションモデルに基づいた計測方法であり、特に「ラストクリックアトリビューション」を採用している場合に顕著です。
例えば、ユーザーが2月1日に広告をクリックし、その後数日間検討した上で2月5日に商品を購入した場合、広告管理画面上では2月1日にコンバージョンが記録されます。しかし、実売数としては2月5日に購入が計上されるため、このズレが集計データの乖離を引き起こします。特に、検討期間が長い高額商品やBtoB商材などでは、このタイムラグが数週間に及ぶこともあり、月単位でのレポートを作成した際に大きな差異が生じることがあります。
また、Googleアナリティクスや一部の広告プラットフォームでは、コンバージョン発生日に基づいて計測されることもあります。このように、ツールごとに異なる計測基準が採用されているため、同じ広告キャンペーンでもレポート上の数値が大きく異なることがあります。このズレを理解しないまま広告効果を評価すると、誤った分析結果を導いてしまう可能性があるため注意が必要です。
この問題に対処するためには、広告管理ツールと実売データを突き合わせる際に、アトリビューションモデルや計測基準の違いを考慮することが重要です。また、検討期間が長い商材の場合には、一定期間のデータを遡って分析することで、より正確な広告効果を評価することができます。クライアントや上司への報告時には、計測基準の違いによる数値のズレについても説明し、透明性の高いコミュニケーションを心掛けることが重要です。
サイト外での売上が含まれている
実売数とコンバージョン数の乖離を引き起こすもう一つの要因として、ウェブサイト上で完結しない売上が実売数に含まれているケースがあります。多くの企業では、ウェブサイト経由の注文だけでなく、電話注文や店舗での直接購入といったオフラインのチャネルも併用しています。このようなオフラインでの購入データが実売数に含まれると、広告管理画面上で計測されたコンバージョン数と実売数との間に乖離が生じます。
例えば、ユーザーがウェブサイトで商品を見た後、掲載されている電話番号に直接電話して注文を完了させた場合、広告管理ツールではこのコンバージョンを計測できません。同様に、オンラインでクーポンを取得し、実店舗で商品を購入した場合も、広告管理画面には反映されないケースがあります。このようなオフラインコンバージョンは、特に高額商品やサービス業において頻繁に発生します。
この問題に対処するためには、電話発信コンバージョンの設定やオフラインコンバージョンのインポート機能を活用することが有効です。例えば、Google広告では、電話番号をクリックした回数を計測する「電話発信コンバージョン」を設定できます。この機能を活用すれば、ユーザーがスマートフォンから直接電話をかけた回数を把握でき、ウェブサイト外でのアクションも一部計測可能になります。
さらに、オフラインでの購入データを広告プラットフォームにインポートすることで、オンライン広告の効果をより正確に評価できます。このプロセスには、CRMシステムと広告管理ツールを連携させることが必要ですが、これによりオンライン広告がオフライン売上にどの程度貢献しているかを可視化することができます。
しかし、これらの計測方法にも限界があるため、最終的には広告効果を評価する際に、オンラインとオフライン両方のデータを総合的に分析することが重要です。特に、オムニチャネル戦略を採用している企業では、各チャネル間のデータの統合と整合性を保つことが成功の鍵となります。クライアントや上司への報告時には、ウェブサイト上で完結しない売上が存在することを説明し、オンライン広告の真の効果を適切に伝えることが求められます。
クロスデバイス計測の差異
近年、ユーザーのデジタル行動が多様化し、スマートフォンやタブレット、PCなど複数のデバイスを横断してインターネットを利用することが一般的になっています。このような行動パターンの変化は、広告運用におけるコンバージョントラッキングにも大きな影響を与えています。特に問題となるのが、クロスデバイスコンバージョンの計上における違いです。クロスデバイスコンバージョンとは、ユーザーがあるデバイスで広告をクリックし、その後別のデバイスで購入や問い合わせなどのコンバージョンアクションを完了した場合に発生します。
例えば、ユーザーがスマートフォンで広告をクリックし、その後PCで商品を購入した場合、広告管理ツールによってはこの行動を一つのコンバージョンとして認識できないことがあります。Google広告やFacebook広告のような大手プラットフォームでは、ログイン情報やCookieを活用してユーザーの行動を追跡し、クロスデバイスコンバージョンを計上できる機能が備わっています。しかし、これらのプラットフォームでも完全な追跡は難しく、特にユーザーがログインしていない状態で複数のデバイスを使用した場合、正確な計測は困難です。
この計上の違いにより、実売数と広告管理画面上のコンバージョン数に乖離が生じることがあります。例えば、Google広告ではクロスデバイスコンバージョンがデフォルトで含まれている場合がありますが、他の広告プラットフォームでは含まれていないこともあります。この違いを理解せずにデータを比較すると、実態と異なる評価をしてしまう恐れがあります。そのため、クロスデバイスコンバージョンの設定や計測基準を事前に確認し、適切なデータ分析を行うことが重要です。
Cookie制限によるトラッキング不足
もう一つ、広告トラッキングの精度に大きな影響を与えている要素として、Cookie情報の遮断があります。従来、多くのコンバージョントラッキングはブラウザのCookie情報に依存していました。ユーザーが広告をクリックした際、その情報をCookieに保存し、その後の行動を追跡してコンバージョンを計測していました。しかし、近年のプライバシー保護の強化により、Cookieの利用には大きな制限が加わっています。
特にAppleのSafariブラウザに導入されたITP(Intelligent Tracking Prevention)や、Google ChromeによるサードパーティCookieの段階的な廃止など、主要なブラウザはユーザーのプライバシーを保護するためにトラッキングを制限する機能を強化しています。これにより、従来のCookieベースのトラッキング手法では、ユーザーの行動を正確に追跡できないケースが増えています。その結果、広告管理画面上のコンバージョン数が実売数よりも少なく計測されるという乖離が発生します。
また、ユーザー側でも広告ブロッカーの利用やブラウザ設定の変更によって、自らの行動を追跡されないようにする動きが広がっています。これらの要素が重なることで、広告運用者にとっては正確なデータ取得がますます難しくなっているのが現状です。対策としては、サーバーサイドトラッキングの導入や、ファーストパーティデータを活用したトラッキング手法への移行が求められています。
乖離を防ぐための対策
実売数と広告管理画面上のコンバージョン数に乖離が生じた場合、まずはその原因を特定することが重要です。コンバージョンタグの設定ミス、計測方法の違い、クロスデバイスコンバージョンの計上漏れ、Cookie情報の遮断など、様々な要因が考えられるため、一つひとつ丁寧に確認していく必要があります。特に、広告管理ツールの設定を見直し、タグの設置箇所やカウント方法、クロスデバイスコンバージョンの有無などを徹底的にチェックすることが求められます。
また、乖離の原因が特定できた場合は、その情報をクライアントや上司にわかりやすく説明することが大切です。広告管理画面上の数値だけでは正確な広告効果を評価できないことを伝え、実売数やオフラインでの購入データも含めた総合的な分析を提案することが信頼関係の構築につながります。加えて、広告配信の目標設定にも乖離を考慮し、現実的な数値を基準とすることで、より精度の高い広告運用が可能になります。
さらに、今後のトラッキングの精度向上に向けて、サーバーサイドトラッキングやコンバージョンAPIの導入を検討することも重要です。これらの手法は、ブラウザ上での制限を回避し、より正確なデータ収集を可能にします。また、ファーストパーティデータの活用や、ログインユーザー情報を基にしたクロスデバイス計測の強化など、ユーザーデータを安全かつ効果的に活用する戦略も有効です。
まとめ
実売数と広告管理画面上のコンバージョン数の乖離は、広告運用において避けては通れない課題です。クロスデバイスコンバージョンの計上の違いや、Cookie情報の遮断といった技術的な問題は、広告の効果測定に大きな影響を与えます。しかし、これらの問題を適切に理解し、対策を講じることで、より正確な広告運用が可能になります。
重要なのは、単に広告管理画面上の数値だけに頼るのではなく、実売数やオフラインデータを含めた包括的な分析を行うことです。また、計測方法やトラッキング技術の進化に柔軟に対応し、常に最新の手法を取り入れる姿勢も欠かせません。広告運用者としては、こうした課題に対して積極的に向き合い、クライアントや上司に対しても透明性の高い説明を行うことで、信頼性の高い運用を実現できるでしょう。最終的には、広告の本来の目的である売上やブランド認知の向上に向けて、最適な戦略を構築していくことが成功への鍵となります。